
こんにちは!DMM.com プラットフォーム開発本部 第1開発部 ユーザーレビューグループ マネージャーの室木です。
突然ですが、人事評価のプロセスに課題を感じているマネージャーや人事担当者の方はいらっしゃらないでしょうか?
- 「評価項目が複雑で、メンバー一人ひとりの実績を正確に把握するのが大変だ…」
- 「毎月の記録やフィードバックに多くの時間がかかり、本来向き合うべきメンバーの育成に集中できない…」
- 「チームの雰囲気やモチベーション管理(vibe-management)にも十分な時間を割けない…」
このような運用上の課題は、多くの組織で共通するものではないかと思います。
私たちユーザーレビューグループでも、人事部が設計した、充実した評価制度を、より効果的に運用するための方法を模索していました。
この記事では、私たちがこの評価制度の運用に対して、LLM(大規模言語モデル)を活用して人事評価の効率化と質的向上を目指す取り組みについてご紹介します。
本記事が、同じような運用上の挑戦に取り組む人事やマネージャー、そしてAI導入を検討するIT部門の皆様にとって、具体的なヒントとなれば幸いです。
充実した評価制度をより効果的に運用するための挑戦
DMMの評価制度は、個人の成長と事業への貢献を多角的に測るために、人事部の方が綿密に設計した非常に充実したものです。
この制度の価値を最大限に活かしながら、評価プロセスの運用面において主に2つ取り組んでいきたいと考えています。
-
多角的な評価項目の効果的な運用
DMMの評価制度は、複数の評価項目で構成された包括的なシステムです。
- 等級評価
- 各等級で求められる達成基準をメンバーが満たしているかを判定します。
- 基本的な業務遂行能力から、専門性を活かした組織貢献、経営レベルの影響力まで、12の幅広いレベルが定義されています。
- 行動評価
- DMMのTech Visionを体現する「Agility(敏捷的)」「Motivative(意欲的)」「Attractive(魅力的)」「Scientific(論理的)」の4つの行動指針(以下Tech Value)に基づき、日々の行動を評価します。
- 半期目標評価
- 所属グループにおける運用に基づき、グループ目標に対する個人の目標達成度を評価します
これらの項目を正確に評価するためには、日々の業務における具体的な行動や成果を細かく把握する必要があります。
- 等級評価
-
運用効率の向上
この充実した評価項目を適切に運用するためには、マネージャーとメンバーの双方に相応の時間投資が必要となります。
- 毎月の具体的な業務内容や成果を記録・精査・判断する必要があります。
- 評価の客観性や一貫性を担保することが難しく、評価者によるブレが生じやすくなります。
- 結果として、評価業務そのものに忙殺され、メンバーとの対話や育成といった、より本質的なコミュニケーションの時間が圧迫されてしまいます。
LLMで解決を検討:議事録から評価レポートを自動生成する4ステップ
これらの運用上の挑戦に対して、私たちはLLMを活用した評価プロセスの効率化に着手しました。
目指したのは、AIに任せるべき作業と、人間が注力すべき対話や育成を明確に区別し、もっと『人』の時間を創り出すことです。
この取り組みにおいて、私たちはAIを「膨大なデータをまとめてくれる、自分のサポートをする部下の一人」として位置づけています。
AIが作成する議事録や評価レポートは、あくまで「たたき台」であり、最終的な判断や決定は必ずマネージャーが行います。
ポイントは下記です。
- 議事録: AIが出力した議事録の内容は、マネージャーが簡易的に確認し、必要に応じて修正を加えます。
- 評価レポート: AIが抽出した評価内容は、あくまでたたき台として扱い、マネージャーが内容を精査し修正します。
- 最終確認: たたき台の内容について、必ずマネージャーとメンバーが確認し合い、双方が合意できた内容にすることがもっとも大切です。
この「AIはサポート、判断は人間」という原則により、効率化と品質の両立を目指しています。
具体的なプロセスは以下の4つのステップで構成されます。

Step 1: AIによる議事録の自動作成
まず、システム開発に関わる全ての会議をGoogle Meetで実施し、AIによる議事録を自動で作成します。
これにより、議論の内容が網羅的にテキストデータとして記録され、後の情報抽出のベースとなります。
Step 2: 評価項目に関連する情報をAIが自動抽出
次に、自動生成された議事録や各メンバーが完了したタスク情報をインプットとして、LLMが等級評価や行動評価に該当する内容を自動で抽出します。
例えば、「Aさんが主体的に改善提案を行い、数値目標の達成に貢献した」といった記述をTech Valueの「Agility」や「Scientific」に関連する実績としてピックアップします。
Step 3: 1on1での内容確認と認識合わせ
AIが全てを決定するわけではありません。
抽出された実績レポートの内容は、必ずメンバーとマネージャーの1on1で確認します。
このプロセスを通じて、AIの抽出内容に事実との齟齬がないか、文脈の誤解がないかをお互いにすり合わせます。
Step 4: 月次実績として記録・蓄積
1on1で確認が取れた内容は、個人の正式な月次実績として記録・蓄積されます。

なぜ月次での記録が重要なのか
私たちは2025年3月から8月末まで、半年間の議事録をまとめて評価に活用する実証実験を行いました。
しかし、半年分の議事録は膨大な量となり、評価に使えるデータとして整理・分析することが現実的ではないことが判明しました。
月次で区切ることにより下記効果が期待出来ます。
- 議事録の量が適切な範囲に収まり、AIによる情報抽出の精度が向上します。
- メンバーとマネージャーの双方が、記憶が鮮明なうちに内容確認できます。
- 評価の根拠となる具体的な行動や成果を見落とすリスクが大幅に軽減できます。
この実証実験の結果を踏まえ、月次での実績記録・蓄積というアプローチを採用します。
これらのデータは、半期ごとの最終評価の際に客観的なエビデンスとして活用されるだけでなく、将来的に評価プロセス自体の継続的な改善や、組織全体の成長分析にも繋がっていきます。
具体的なプロンプトと出力サンプル
上記のStep 2で使用するLLMプロンプトと出力結果のイメージをお見せします。実際のプロンプトは非常に詳細ですが、ここでは核心部分を簡略化してご紹介します。
サンプルプロンプト(簡略版)
# Tech Value評価抽出プロンプト あなたは人事評価の専門家として、議事録から対象者のTech Value行動評価に関する情報を抽出してください。 ## Tech Value 4軸 1. **AGILITY(敏捷的)**: 変化への適応、継続的改善、失敗からの学習 2. **MOTIVATIVE(意欲的)**: チーム動機付け、目的共有、リーダーシップ 3. **ATTRACTIVE(魅力的)**: 社外発信、ブランディング、知見共有 4. **SCIENTIFIC(論理的)**: データドリブン思考、論理的分析、建設的問題解決 ## 抽出指示 議事録から各軸に該当する具体的な行動や発言を抽出し、評価基準(A/B/C/D)で評価してください。 根拠となる議事録の内容を必ず引用してください。 ## 入力情報 - 対象者名: [氏名] - 現在の等級: [弊社で決められた等級] - 評価期間: [YYYY年MM月] - 議事録データ: [該当月の全議事録]
出力サンプル(架空の人物での例)
## 基本情報 - 評価対象者: 田中太郎 - 現在の等級: [弊社で決められた等級] - 評価期間: 2024年09月 - 評価者: 山田二郎 ## Tech Value 4軸評価 ### AGILITY(敏捷的) **今月の実績**: - 調整・改善活動: レビュープロセスの改善提案を行い、チーム全体のレビュー時間を20%短縮 - 継続的学習・適応: 新しいフレームワークの導入について、実証実験を主導 - 改善サイクル実践: 週次振り返りでの改善点を翌週に即座に適用 **評価**: B(期待を上回る成果・行動) **コメント**: XX等級として期待される以上の改善活動を主体的に実施 ### MOTIVATIVE(意欲的) **今月の実績**: - コミュニケーション・目的共有: スプリント目標について、チーム全体で目的を再確認する場を設定 - リーダーシップ・巻き込み: 新人メンバーのオンボーディングを積極的にサポート **評価**: C(期待通りの成果・行動) **コメント**: 現在の等級相応の活動を継続実施 ### ATTRACTIVE(魅力的) **今月の実績**: - 知見共有・発信: 社内LT会で技術調査結果を発表、他チームからも好評 **評価**: C(期待通りの成果・行動) **コメント**: 社内での知見共有は継続的に実施している ### SCIENTIFIC(論理的) **今月の実績**: - 数値ベースコミュニケーション: パフォーマンス改善施策について、具体的な数値データを用いて効果を報告 - データドリブン提案: ユーザー行動分析に基づく機能改善提案を実施 **評価**: B(期待を上回る成果・行動) **コメント**: 数値根拠に基づく提案・報告が継続的に実施されている ## 議事録からの抽出根拠 ### AGILITY関連の根拠 - BE定例会議: 9/15 - 「現在のレビュープロセスに課題を感じており、改善案を検討したい。来週までに具体案をまとめます」 - 振り返り会議: 9/22 - 「田中さんの提案したレビューガイドラインにより、今週のレビュー時間が大幅に短縮されました」 ### SCIENTIFIC関連の根拠 - スプリントレビュー: 9/30 - 「パフォーマンス改善により、ページ読み込み時間が平均2.3秒から1.8秒に改善されました」(田中発言)
このように、AIが議事録から関連する行動を抽出し、評価軸に沿って整理することで、マネージャーが評価する際の材料を効率的に準備できます。
AI導入がもたらす5つの効果:効率化の先にある未来
この仕組みを導入することで、私たちは5つの大きな効果を期待しています。
-
時間効率の向上
- 議事録作成や評価材料収集が自動化され、マネージャーの評価作業時間が大幅に短縮されます。
- 創出された時間で、メンバーとの1on1やキャリア相談、育成計画の策定、チームの雰囲気作りやモチベーション管理(vibe-management)といった、より付加価値の高いコミュニケーションに集中できます。
-
評価の質向上
- 客観的な記録に基づいた評価が可能になります。
- 評価基準が一貫して適用されるため、公平性が高まります。
- 個人の記憶や印象に頼ることで生じていた見落としや主観的偏見が軽減されます。
-
透明性の確保
- 「なぜこの評価になったのか」という評価根拠が明確になります。
- メンバー自身も自分の実績を客観的なデータで振り返ることができ、評価に対する認識共有がスムーズになります。
- 具体的で納得感のあるフィードバックが可能になり、メンバーの成長を促進します。
-
継続的改善
- 評価データがデジタルで蓄積・分析しやすくなるため、評価プロセス自体の改善に繋がります。
- 組織全体の強みや課題が可視化され、組織全体の成長を促進する土台となります。
-
チーム文化の向上
- 時間と心に余裕がうまれることで、マネージャーがチームの雰囲気作りやモチベーション管理(vibe-management)に集中できる時間が増加します。
- メンバー間のコミュニケーション促進や組織文化の醸成に注力可能になります。
- 評価の透明性向上により、チーム全体の信頼関係と士気が向上します。
導入に向けた検討事項と今後のアクション
もちろん、この仕組みを実現するにはいくつかのハードルがあります。
私たちは、技術・運用・導入プロセスの3つの観点で検討を進めています。
- 技術的要件: Google MeetのAI議事録機能の活用、LLMによる評価項目抽出システムの構築、そして既存の人事評価システムとの連携が鍵となります。
- 運用面の課題: AIの抽出精度をいかに高めるかというチューニングや、この新しいプロセスに対するメンバーへの丁寧な説明と理解促進が不可欠です。
- 段階的導入: 全社一斉導入ではなく、まずはパイロットグループでの試験運用から始め、フィードバックを元に改善を重ねながら、他のグループへと展開していく計画です。
具体的には、以下の3フェーズで進めており、現在はPhase2を行っています。
- Phase1: 検証・準備期間: 技術検証、システム設計、関係者との調整をします。
- Phase2: パイロット運用: 1〜2つのグループで試験運用し、課題を洗い出します。
- Phase3: 他グループへの展開: 改善を重ねながら、他部署へ展開していきます。
おわりに
LLMをはじめとするAI技術の進化は、単なる業務効率化のツールに留まりません。
今回ご紹介したDMMの取り組みは、AIの活用によって人事評価のあり方そのものを、より客観的で、透明性が高く、公平なものへと変革する挑戦の一歩です。
AIに記録や整理といった作業を任せることで、私たち人間は、対話を通じてメンバーの成長を支援し、未来を共に考えるという、本来もっとも大切にすべき業務に時間とエネルギーを注げるようになります。
この「もっと『人』の時間を創り出すための挑戦」は、まだ始まったばかりです。
今後の進捗や得られた知見についても、このDMM Developers Blogで発信していきたいと考えています。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

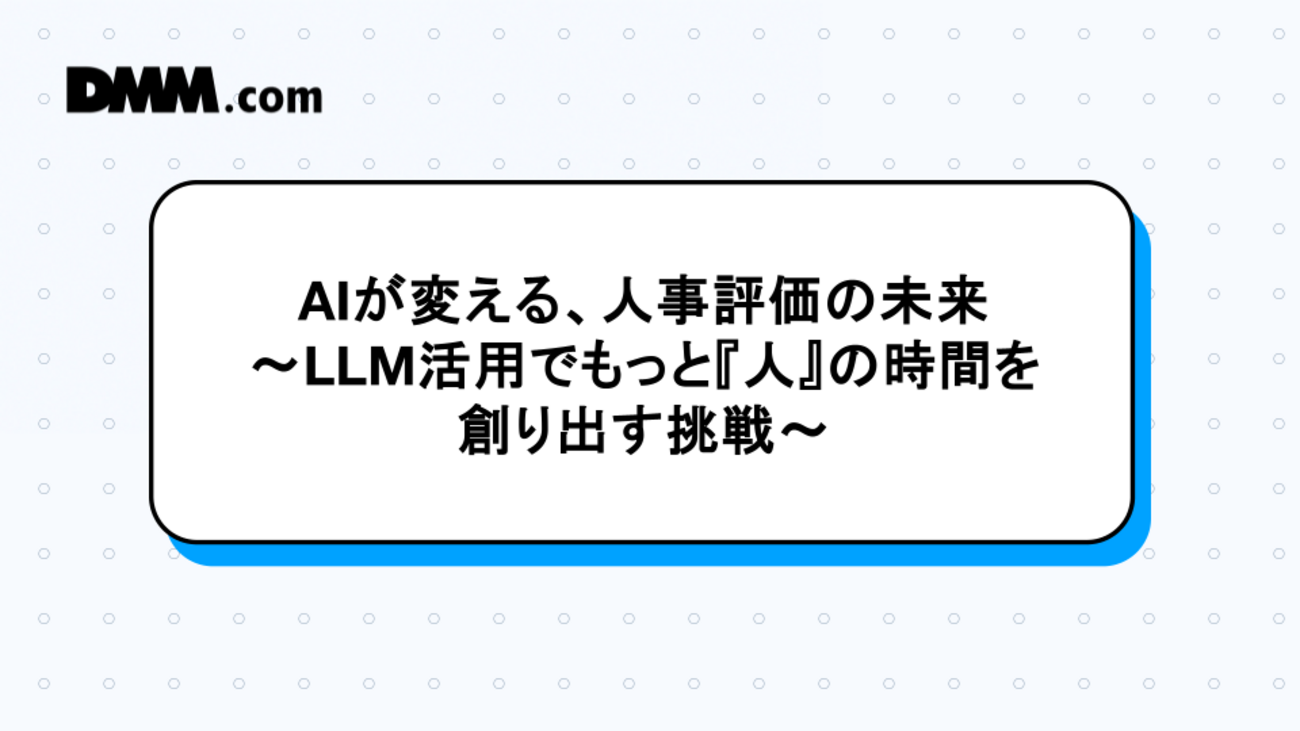
コメント