先日サンフランシスコで開催されたSalesforce社主催のイベント「Dreamforce 2025」に現地参加してきました!私自身はSalesforce社が提供しているiPaaS製品「MuleSoft」を用いたプロジェクトに携わっているため、情報収集や交流を目的に参加いたしました。
本記事では、現地参加して感じた会場の雰囲気や公開された情報の共有、そしてイベント参加を通して感じたことなどお伝えできればと思います。
AIエージェントを活用した業務推進はもう実用レベルで進んでいるんだなと強く感じる一方で、ITベンダ社員としてこれからできることは何か考える良いきっかけになったと感じたため、そのことについて触れたいと思います。
また、同じくDreamforceに参加した KotaF さんも参加レポートを書いております。一部重複する内容もありますが、お互いに補完する内容になっておりますので、是非、こちらの記事もご参照ください。
【AIエージェントはここまで来た】Dreamforce 2025 参加レポート
- Dreamforce 2025について興味がある方
- Salesforceの製品や最新動向について知りたい方
- AI活用の最新動向を知りたい方
Salesforce社が毎年開催している世界最大級のカンファレンスイベント。
Salesforce製品やサービスの新機能発表、ワークショップやハンズオンなどのセッション開催、およびパートナー企業の展示などが行われていました。
また、コミュニティの貢献を重視しており、Trailblazer(顧客・パートナー・従業員などSalesforceに関わるすべての方)に対して魅力的なコンテンツ・体験を提供することも目的とのことです。個人的に印象に残っているのは、 コミュニティで活躍した方に「ゴールデンフーディ(Golden Hoody)」と呼ばれる金色のパーカーを送り 、プロダクトごとのセッションで讃えていたことです。世界中のTrailblazerの前で祝福される文化は素晴らしいな、と感じました。
会場の雰囲気や盛り上がり
モスコーン・センターという展示会施設を中心に周辺のホテルも含め会場として整備されており、各地で基調講演や展示など開催されていました。
Salesforceのマスコットキャラクターを模した石像が設置されていたり、会場は煌びやかな装飾で彩られていたりと、さながらお祭りのような雰囲気。2日目夜にはメタリカやベンソンブーンといった人気アーティストを招待してのライブが開催されたりと、ビジネスの場であっても思い切り楽しむという文化を肌で感じることができました。
全体で3日間開催されていましたが、連日大勢の人で溢れかえっており人気の基調講演は長蛇の列になることも……。私も参加するために早めに並んで備えました。

ここでは、参加した講演内容について記載いたします。
Agentforce 360による「エージェンティック エンタープライズ」
「エージェンティック エンタープライズ」が今年のメッセージとして据えられており、私が参加した基調講演はすべてがそれに基づき構成されていました。昨年リリースされたAgentforceはAgentforce 360へ進化し、プラットフォームとして顧客・従業員・エージェントがつながるサービスを提供できるようになると紹介されていました。
加えてAgentforce 360の主要アップデートとして4つの機能について紹介があり、それらを活用した業務シナリオが共有されました。
- Intelligent Context(コンテキストの強化)
- Agentforce Voice(音声チャネル対応)
- Agentforce Builder(自然言語での構築)
- Agentforce Script(制御性の向上)
音声チャットボットのピッチやトーンを自由にカスタマイズするといったデモや、それら業務実装をプラットフォーム上で完結している様子が事例交えて紹介されていました。
Agentforce OSとしてのSlack
特に印象的だったのが、SlackをAgentic OSとして再定義(Key Noteでは Reimagined と呼んでいました)し、AIエージェントがさながら組織・チームの一員として、
一つのコミュニケーションスペースで協調する世界観が提示されたことです。
具体的には、Slack上のチャットボットがAgentforceやその他のAIエージェントと統合され、以下のようなユースケースが紹介されています。
- サポートチームがAIエージェントを活用しながらインシデントを分析し、必要に応じて関連エンジニアを巻き込んで対応を進めていく。
- セールスチームがAIエージェントを活用しながらマーケティング分析をし、AIエージェントが有効なキャンペーンを立案し、実施後の効果のトレースも行う。
- SlackBotがパーソナライズされたAIエージェントとして一人一人の全ての作業をサポートしていく。
プラットフォームやサービスとしてAgentforce 360製品を利用することが前提にはなりますが、AIエージェントを活用した高速実装やサービス間のデータ連携・AIによる分析などは、開発効率化・生産性の観点で魅力的に感じました。

事例紹介を中心に添えた発表
パートナー企業を交えたディスカッション形式の発表が多いことも印象に残りました。
自社ではどのように活用しているか、導入によってどれだけの効果が出たか…などが各パートナー企業より語られており、AI活用による業務実装はすでに実用的であることがアピールされていました。
パートナー企業として登壇していたのは多くがユーザ企業の方だったと思います。AIエージェントの活用によりユーザ企業側でバンバン開発を進めていく未来は日本でも近いのでは、といった感想を持ちました。
MuleSoftに関する発表
ここでは私が携わる機会が多いMuleSoftにフォーカスして、発表内容に触れたいと思います。
MuleSoft Agent Fabric
AIエージェントの一元管理を担う機能として、MuleSoft Agent Fabricが紹介されていました。
もともとMuleSoftではAnypoint PlatformというAPIを一元管理するサービスが提供されていましたが、Agent FabricはAIエージェント向けに整備された機能という印象を持ちました。
講演では以下4つの機能についてフォーカスされており、AIエージェントの管理・統合への有用性が語られていました。
- MuleSoft Agent Registry(組織内外のAIエージェント一元管理)
- MuleSoft Agent Broker(AIエージェント・ツール間の連携およびタスク振分けの自動化)
- MuleSoft Agent Governance(AIエージェントのセキュリティ・ガバナンス管理)
- MuleSoft Agent Visualizer(AIエージェント間の連携状況可視化)
4機能の中では MuleSoft Agent Broker に特に関心を持ちました。
MuleSoft Agent Brokerは、AIエージェントやツール間をビジネスドメイン単位で整理し、Agent Brokerが最適なAIエージェントへ動的にタスクを割り振ることを可能とします。また、Agent Brokerは選択したLLMを基盤としA2A・MCPを介して接続できるとのこと。
AIエージェント(正確にはLLM)には多数のドメインの知識を与えると、あるところから精度が低下していくという課題を抱えています。また、LLMが肥大化することによって、相互運用性も低下していきます。
そのため、AIエージェントを統括エージェントと特化型エージェントに分離し、適材適所でAI同士が連携していくようなアーキテクチャが昨今のAIシステムのトレンドかと思います。
MuleSoftとしても、このようなAIシステムアーキテクチャを採用してAIシステム全体をコントロールしていくと共に、
元からの強みであるシステム間連携との統合を図っていくことで、プロダクトの差別化を図っているように感じました。
説明を聞くかぎり、非常に有用な機能に感じましたが、選択するLLMによる挙動の差異や自動化の精度、カスタマイズ性などについては気になる点がいくつかありました。実際の使用感など確認したいため、早く試したい機能です。
MuleSoft Vibes
MuleSoftに最適化されたAI機能を使用したアプリケーション作成や開発が可能になるサービスとして紹介されていました。
もともとローコードによるGUI開発が特徴だったMuleSoftですが、自然言語インタフェースを通じたアプリケーション開発・運用が可能になるとのことで、開発の敷居を下げてくれるのかが気になります。
一方で、AIコーディングツールとしてはGitHub CopilotやClaudeなどが先行ツールとして存在しますし、
MuleSoftのフローは最終的にXMLに落とし込まれるため、これらの先行ツールを使った開発もある程度可能だと考えられます。
もちろん、MuleSoftに最適化されたAIコーディングツールという強みはあると思いますが、
エンタープライズシステム開発における様々な要求・制約に応えられるレベルに到達しているのか、先行ツールを凌駕する効果を得られるのか、
私が所属するチームでも検証は進めていきたいと感じました。
また、その中で MuleSoft Vibesならではの制約や開発ノウハウも得られると思うので、
そういったナレッジをパートナー企業としてMuleSoft Vibesにフィードバックすることで、今後の更なるUpdateにも期待したいと思います。
「業務に対するAI活用の実用化」を肌で感じたイベント
Dreamforce 2025は、Agentforce 360をベースにAI活用による業務実装が実用的なレベルまで来ている、ということを感じたイベントでした。どの基調講演でもパートナー企業とのディスカッションを盛り込んでおり、実用性についてアピールされていました。
AI活用によるシステム開発は、日本でも主流になる未来が近いと感じました。
自担当のプロジェクト導入を見据えた取り組み
「Agentforce 360すげー。もう誰でもAI使って業務実装に関われるじゃん」という感想も少し持ちました。たしかに使いこなせるとかなり便利なサービスですが、使いこなすためのノウハウ整理やアーキテクチャ検討・人材育成などはこれから注力ポイントになると考えられます。注力ポイントを押さえプロジェクト推進していける人材となれるよう、自業務の中で意識的に取り組んでいきたいとあらためて感じました。
身近なところからということで、私が携わる機会が多いMuleSoftにおいて検討ポイントだと感じたところを最後にまとめました。
AIエージェントのガバナンス・オーケストレーションのベストプラクティス検討
AIエージェント導入による業務効率化に注目が集まっていますが、開発が進んでいくにつれAIエージェントの乱立やガバナンス不全に陥る可能性も考えられます。AIエージェントのガバナンス強化に重要な役割を果たすとしてMuleSoftが説明されていました。
たしかに元々の強みであったガバナンス強化や機能間のオーケストレーションという観点では強力なツールになると思います。
一方で、MuleSoftが提唱するAPI-led Connectivityの実現には、機能分割やシステム間連携方式の検討が従来でも重要とされています。
実プロジェクトではこのようなAPIアーキテクチャの設計は引き続き重要な観点だと思いますし、
AIエージェントの統合においてAPI-led Connectivityを引き続き活用していく部分、変えていかなければいけない部分を見極めた上で、ベストプラクティスを生み出していく取り組みを進めていきたいと思います。
Dreamforceで発表された新機能では、エージェントやツール間の連携を強化するAgent Brokerをどう扱えるかが重要なのではと感じたため、Agent Broker自体の機能確認やエージェントとの連携方式など調査したいと思います。
AIエージェントを組み込んだシステム検討が可能なアーキテクト育成
これからのシステム開発では、AIエージェント・API・既存システムが相互連携する処理方式を採るシステムが増加すると予想しています。
そのようなシステム開発では、接続する関連サービスの仕様や制約を押さえた上で、AIに関する知見も踏まえて全体最適を考えられるアーキテクトが求められます。
そのようなアーキテクトに求められるのはどのようなスキルか、育成するためにはどのような学習ロードマップが必要なのか、ということを整理し人材育成を進めていくことも重要な課題だと思いました。
おわりに
Dreamforce 2025に参加しての感想と、AIエージェント全盛時代においてどのような準備・対応ができるのか考えた内容など、この記事で記載いたしました。
近い将来、AI活用による業務開発が当たり前になる時代に向け、自己のスキルを磨いて準備を進めたいと思います。
Source link

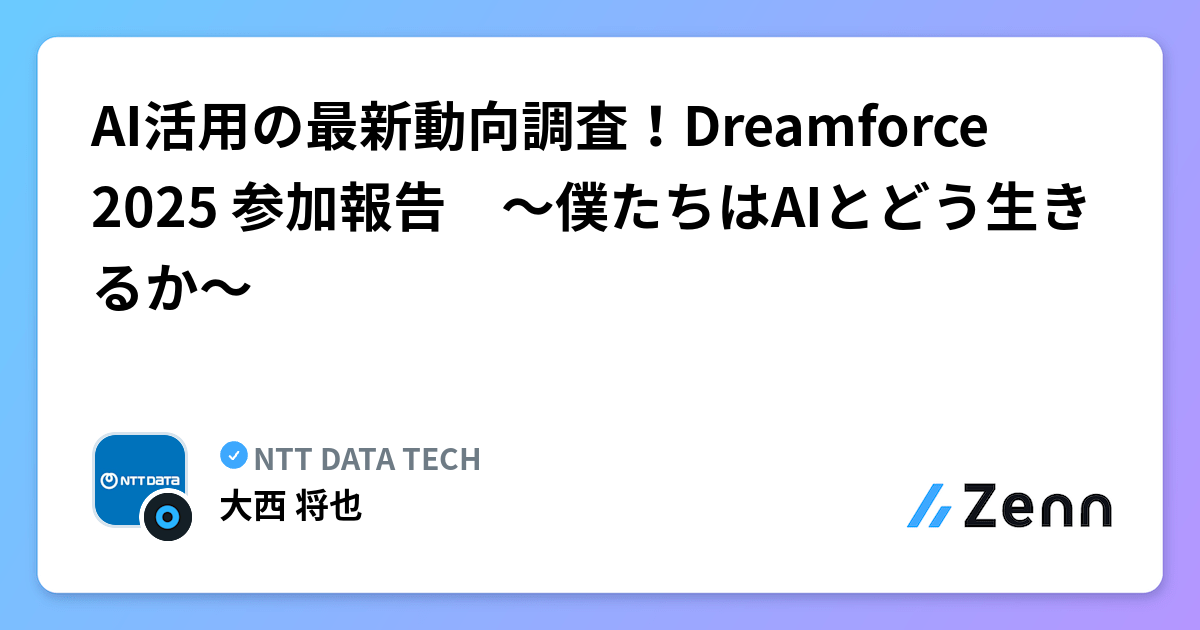
コメント