

採用市場での競争が激化する中、人材を「募集」するのではなく「獲得」する「タレントアクイジション」という新たな採用概念に注目が集まり始めている。そんな中、TalentXが「タレントアクイジション」をテーマにした大型イベントとしては日本初となる「Talent Acquisition Conference 2025」を開催した。今回は、そのイベントの内容をお届けする。(以下、発言は要約)
Talent Acquisition Conference 2025とは
タレントアクイジションの考え方を日本企業に広め、人事が今できる取り組みを共に考え学ぶ大型カンファレンス。従来の欠員補充型採用ではなく、中長期的な視点で潜在層に戦略的にアプローチし、競合と争わず人材を獲得する仕組みを探る場を目指して開催された。
スペシャルセッション「タレントアクイジションが導く経営価値とは」
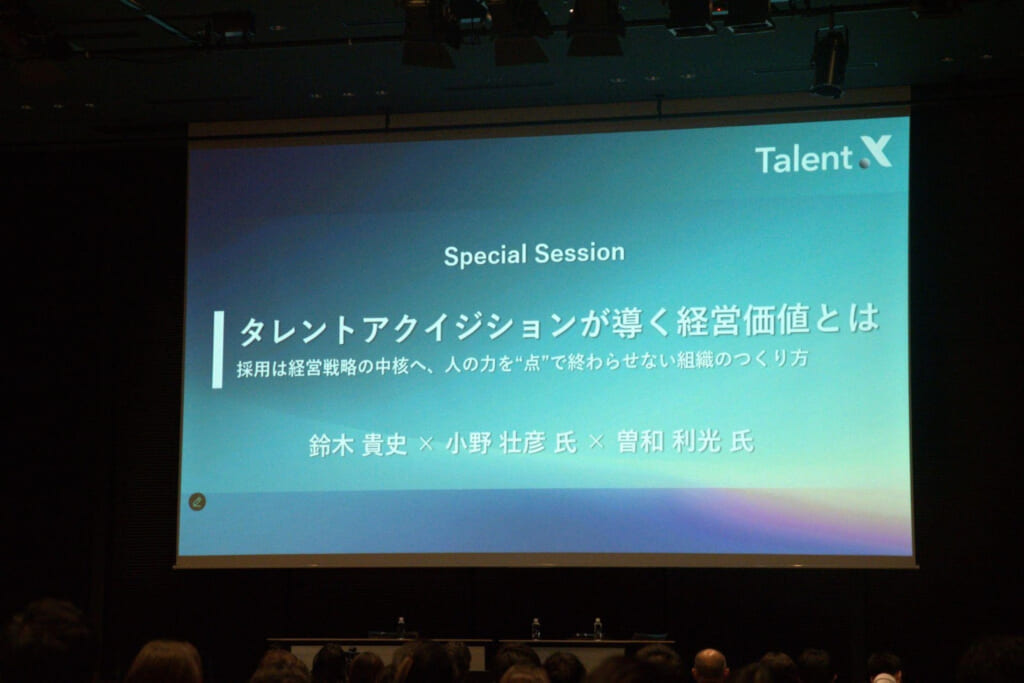
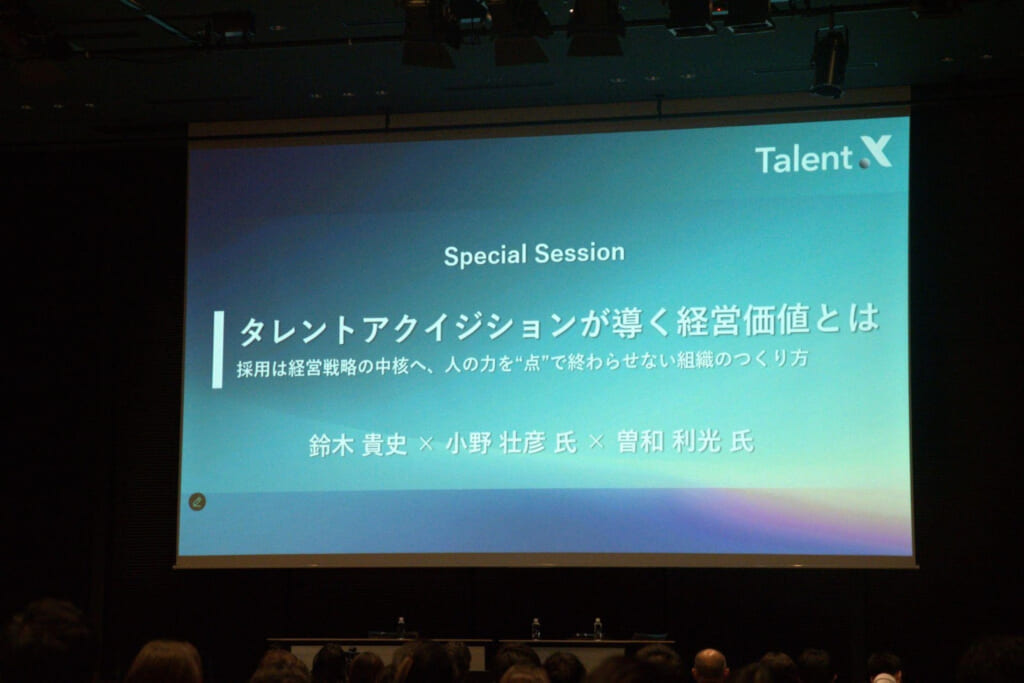
スペシャルセッションでは、TalentX代表取締役社長の鈴木貴史氏がモデレーターとなり、株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズのディレクター小野壮彦氏と、株式会社人材研究所代表取締役社長の曽和利光氏を迎え、「タレントアクイジションが導く経営価値とは」をテーマにしたディスカッションが行われた。
採用はもはや人事部門の専任業務ではなく、経営そのものに直結する戦略テーマになりつつある。企業の人材獲得力が成長性に直結する時代となった今、日本企業がどのようにタレントアクイジションに着手し、自社の経営価値へと転換すべきか、議論が展開された。
なぜ日本でタレントアクイジションが浸透しにくいのか
セッションでは、まず「なぜ日本でタレントアクイジションが浸透しなかったのか」という問いから議論がスタートした。
小野氏は、グローバルと比較した日本の特徴として、管理職の給与水準の低さを指摘。諸外国に比べると日本の管理職の給与が低く抑えられており、エージェントフィーを支払って採用を外部に委託する方が経済合理性が高いという考え方が根付いているという。さらに、従来の日本の中途採用は「欠員補充」という短期的な視点に偏っている点もタレントアクイジションが浸透しにくい一因だと分析した。


小野氏「しかし近年、その状況が変わりつつあります。これまで新卒中心主義を貫いていた企業も、徐々にマネジメント・リーダー層を戦略的に採用する必要性を認識し始めました。競争の激しい業界を中心に管理職の給与が上昇し、同時にエージェントフィーも高騰。これにより、採用の内製化、すなわちタレントアクイジションへ移行する機運が高まっています」
一方で曽和氏は「足元の採用充足を追いかけるのに必死で、長期的な戦略に着手する余裕がない」と採用現場の実情を語る。さらに、経営層も中長期的な人材戦略を描けていないケースが多く、これがタレントアクイジションが進まない要因だという。
曽和氏「タレントアクイジションを進めるには、中長期の経営戦略から逆算して人員計画を立てる必要があります。ですが、日本にはこうした『動的人材ポートフォリオ』を作れている会社は、大企業を含めてほとんどないと言っていい。経営陣が必要な人材要件を定められない限り、仮にタレントアクイジションの実行体制が整ってもなかなか前に進まないのではないでしょうか」
タレントアクイジションの実践に向けて、日本企業が取り組むべきこと
次のトークテーマは「タレントアクイジション実践のために取り組むべきこと」。
小野氏は、タレントアクイジションが進まない最大の要因は「経営側の理解と切迫度が足りないこと」だと断言し、経営層の意識改革が不可欠だと訴える。タレントアクイジションは人事の仕事だと誤解されがちだが、本質は経営戦略そのものである。この認識を経営層に浸透させ、全社的な当事者意識を醸成することが成功の鍵だと強調した。
小野氏「リクルートの採用部門では、事業部のエースのようなハンター気質の人材で専門チームを構成し、能動的な人材獲得を行なっています。長期的な成長のために、会社のエースを人事に配置するという組織変革ができるかどうか。これがタレントアクイジション実践の第一歩だと思います」
曽和氏は「タレントアクイジションが『攻め』の採用である以上、まず求める人物像(ペルソナ)の解像度を徹底的に高める必要がある」と説明。単に職種で区切るのではなく、その職務で成果を出すために必要なポータブルスキルを特定し、異業種や異職種にまで視野を広げてターゲティングすることが重要だと語った。
さらに「昔のリクルートでは営業職のポテンシャル人材として役者やスポーツマンをスカウトしたことがあった」と事例を挙げ、一見関係ない職種でも、共通のポータブルスキルに着目すれば優秀な人材を発掘できる可能性を示唆した。


曽和氏「社内の職種が100を超える大企業の場合、それぞれに対してペルソナを設計するのは難易度が高いかと思います。その場合は全社員に適性検査を実施し、自社で活躍する人材の特性をデータで分析することも有効です。職種間の異動も考慮しながらハイパフォーマーの共通点を探ることで、客観的かつ効率的に動的人材ポートフォリオを設計できます」
日本とグローバル、タレントアクイジションの立ち位置の違い
続いて小野氏は、グローバルにおけるタレントアクイジションの現状を紹介。当初は人気職種とは言えなかった採用担当の地位が、Googleの取り組みをきっかけに大きく変わったという。
小野氏「2010年頃からGoogleはコンサルタント、エンジニア、人事出身者を混成させた特別チームを作り、タレントアクイジションを実践。そこから優秀なスキルを身につけたタレントアクイジション人材が世に解き放たれ、現在ではタレントアクイジションの専門家が経営幹部として高額な報酬を得ることも珍しくなくなっています」
一方で日本では、タレントアクイジションがまだ独立した専門職として確立しておらず、「人事部の一部」という認識が根強いのが現状だ。
曽和氏は「タレントアクイジションの普及は遠い道のり」としながらも、まずは「タレントアクイジションという言葉が浸透することが、社会が変わっていく一つの最初のステップになる」と、人事や人材業界の関係者がこの概念を周知する重要性を述べた。
モデレーターの鈴木氏も同意しながら、「日本企業が強くなる上ではHRが経営の中心にいなければいけないという意識改革と共に、営業や経営企画のようにタレントアクイジションションに関わる職種が『かっこいい』仕事だという認識を広めていきたい」と意欲を語った。
今後の可能性
最後に、「日本企業が強くなるためには、HRが経営の中心にいなければいけない」という認識のもと、タレントアクイジションが普及した先で起こる未来について議論がかわされた。
曽和氏は、タレントアクイジションが普及すれば、採用がより本質的なマッチングへと進化する可能性を指摘した。
曽和氏「多くの候補者との継続的な関係構築をベースにした採用が実現すれば、必要なタイミングでの人材獲得もしやすい上に、価値観や人間性を理解した上で採用できるようになります。結果的に、採用コスト削減や組織の安定性につながるはずです。さらに、日本の労働人口が減少する中で、これまで活躍のチャンスがなかった人のスキルを活かせる社会になっていくのではないでしょうか」
小野氏は、タレントアクイジションが経営に直結する仕事として再解釈されることで「人事のプロファイルが変わる」と述べる。そして「採用が経営戦略の中核に位置づけられることで、そこで働く個人のキャリアもより戦略的で魅力的なものへと変わっていくはずです」と、採用担当者のキャリアの可能性が大きく広がることを示唆した。
まとめ
日本企業におけるタレントアクイジションの課題と可能性が浮き彫りになったスペシャルセッション。経営層の認識変革、専門性の高い採用組織の構築、長期的な人材戦略の策定など、取り組むべき課題は多いものの、その先には組織の生産性向上や持続的な競争力の獲得という大きな可能性があることが示された。


鈴木氏は最後に「HRを経営の中心に据え、人事の地位を高めていくことが重要です。TalentXとしても『未来のインフラを創出し、HRの歴史を塗り替える』というビジョンの下、皆様とともに取り組んでいきたい」とセッションを締めくくった。
タレントアクイジション特集の第3弾では、本イベントの内容を受け、鈴木氏に単独インタビューを実施。日本におけるタレントアクイジションの可能性と人材業界の展望について深掘りしていく。
元の記事を確認する

