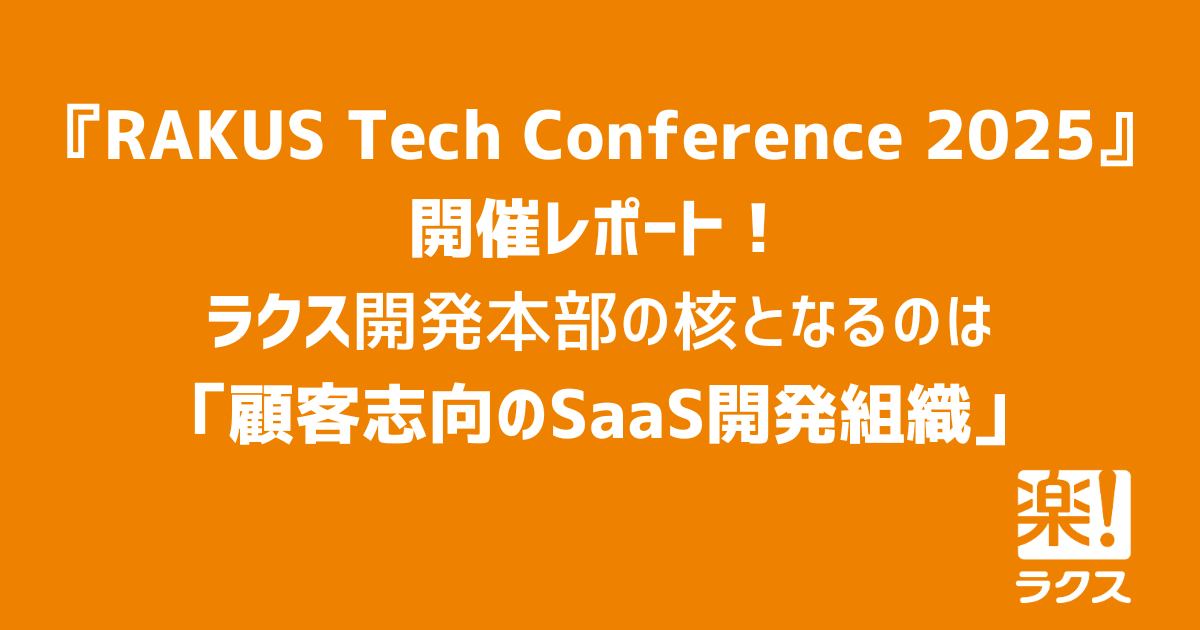
こんにちは!!ラクス技術広報担当です。
2025年8月7日(木)に、オンラインにて「RAKUS Tech Conference 2025」を開催いたしました。平日にもかかわらず、多くの皆様にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じることができました。登壇者、関係者の皆様、そして何よりご視聴いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。
本イベントの開催目的は、私たちラクス開発本部が最も大切にしている「顧客志向」という概念を多くの方に知ってもらうことでした。参加後アンケートの結果から、9割の視聴者の方に「ラクスが顧客志向な開発組織であるという印象が伝わった」という回答をいただき、イベントの目的が果たせたことは大変良かったと思います。
各セッションでは、ラクスのサービスが日々どのように顧客と向き合い、その価値を技術で実現しているのか、7つのセッションを通じて開発の裏側にある「強み」や「想い」をお届けしました。
また、クロージングトークではラクス開発本部のAIの取り組みについてご紹介しました。
本記事では、各セッションで語られた内容をダイジェストでご紹介します。
各セッションの紹介
1. 『楽楽電子保存』開発チームが挑む「AI駆動開発」の全貌
登壇者:楽楽明細開発部 開発2課 小栗 朗、フロントエンド開発課 伊藤 彪我
電子帳簿保存法の改正により市場が3年で3.5倍に拡大する中、『楽楽電子保存』開発チームは、激化する競争を勝ち抜くために「AI駆動開発」による開発プロセス全体の刷新に挑んでいます。
セッションでは、まず設計フェーズにおいて、PMM・PdM・開発者間で分散していたドキュメントをGoogle Docsに一元化し、AIが読み取りやすいよう構造化。AIに設計ドラフトの作成やレビューをさせることで、設計期間を平均30%以上短縮することに成功しました。実装フェーズでは、DevinやGitHub Copilotといった複数のAIツールをタスクに応じて戦略的に使い分け、平均30%の工数削減を実現。さらに、ラクスベトナムとのグローバル開発体制においても、AIによる翻訳やレビュー支援がコミュニケーションコストの削減や業務のボトルネック解消に繋がり、開発力を大きく向上させている事例が紹介されました。
2. 数字と感情で語るスクラム導入効果。『楽楽勤怠』開発チームの変革の軌跡
登壇者:楽楽勤怠開発部 開発1課 加藤 祐也
働き方改革を追い風に市場が成長する一方、圧倒的なマーケットリーダーが不在で競合がひしめく勤怠管理システム市場。後発サービスである『楽楽勤怠』がシェアを拡大するためには、開発スピードとボリュームの向上が必須でした。
そこで白羽の矢が立ったのが、ラクスではまだ主流ではなかった「アジャイル(スクラム)開発」の導入です。本セッションでは、スクラム導入後の具体的な成果が「数字」と「感情」の両面から語られました。数字の面では、リリース案件数が導入後に大幅に増加し、受注件数も過去最高を記録。感情の面では、エンジニアの満足度は10段階中平均8ptと高く、「コミュニケーション頻度が上がった」「チームで助け合いが出来る」といったポジティブな声が多く挙がりました。プロセスの導入だけでなく、失敗を恐れず変化を楽しむマインドの醸成が成功の鍵であることが示されました。
3. 分割と統合で学んだサイロ突破術—『楽楽販売』開発組織10年の軌跡と持続的成長の仕組み
登壇者:楽楽販売開発部 部長 藤井 高志、同 テックリード 山内 覚
年間売上高55億円を超え、SaaS型販売管理システムでシェアNo.1を達成した『楽楽販売』。そのプロダクトの成長を支えてきたのは、10年間にわたる開発組織の変革の歴史でした。
セッションでは、7名体制だった10年前から24名体制の現在に至るまで、組織がどのように変化してきたかが語られました。当初は全員が全ての領域をカバーしていましたが、組織の拡大に伴い、企画、要件、実装といった職能別のチームに分割。しかし、これがチーム間の連携を妨げる「サイロ化」という新たな課題を生み出しました。この課題を乗り越えるため、再び要件から実装、技術負債改善までを一気通貫で担うチームへと統合。日々の接点が多い作業は同一チームで推進すべきであるという学びや、改善の取り組みをチームで推進し、暗黙知を共有する重要性が共有されました。
4. 『メールディーラー』へのAI機能実装─”20年”の歴史を持つ製品への導入プロセス
登壇者:メールディーラーAI開発課 神山 賢太郎、メールディーラー開発課 廣部 知生
2001年に販売開始され、16年連続シェアNo.1を誇る『メールディーラー』。この歴史あるレガシーシステムに、いかにしてAIという新しい技術を迅速に実装したのか、そのプロセスが語られました。
「世はまさにAI戦国時代」 という市場の変化に対し、ビジネスサイドからは「うかうかしているとディスラプトされる」という強い危機感が示される一方、開発サイドではビジネス価値への懐疑的な見方もあり、当初はスピード感にずれがありました。しかし、展示会でAIエージェントへの注目度の高さを目の当たりにし、危機感を共有。ウォーターフォール型開発が主流だった組織の中で、AI開発に特化した課を新設し、完全アジャイル開発にシフト。PMM、PdM、デザイナーが密に連携し、顧客ヒアリングを週1ペースで行いながら高速でPDCAを回すことで、開発スケジュールを大幅に短縮し、価値提供を早めた事例が紹介されました。
5. 新サービス『楽楽請求』!何を作るかより“なぜ作るか” 顧客価値から逆算する開発現場のリアル
登壇者:楽楽請求開発部 開発1課 巽 隆氏、庄禮 有佑
2024年10月にサービスを開始した新サービス『楽楽請求』。ゼロからイチを創り出す過程で直面した、数々の成功と失敗がリアルに語られました。
リリース当初は、ドメイン知識ゼロの状態から書籍や競合サービスの機能分析を基に仮説を立てて開発を進めました(仮説ドリブン)。しかし、リリース後、実業務にそぐわない仕様や、顧客が本当に求めていた機能とのズレが明らかになりました。この経験から、開発プロセスを全面的に見直し、営業やサポートが収集した顧客の声(VoC)を起点とする「VoCドリブン」へと大きく舵を切りました。現在は、2000件を超える要望DBを基に、「何を作るか」よりも「なぜそれが必要なのか」という顧客課題の深掘りを徹底し、顧客が本当に求める価値を提供できる開発体制を築いています。
6. なぜ、成熟市場で”売上120%成長”を続けられるのか?『配配メール』の顧客志向型プロダクト開発戦略
登壇者:ラクスクラウド開発部 配配メール開発課 西尾 敬太
サービス開始から18年目を迎え、国内市場が成熟期にある中で、年間売上成長率120%超を達成し続ける『配配メール』。その力強い成長の源泉は、徹底した「顧客志向型プロダクト開発戦略」にありました。
配配メールは、単なるメール配信ツールから、リード獲得・育成・商談化というマーケティングプロセス全体をカバーするプラットフォームへと進化を遂げてきました。この戦略を支えるのが、「迅速かつ柔軟に価値を届ける」リリース戦略と、「開発者全員が深く顧客を理解する」ための取り組みです。新機能は価値の単位で分割して段階的にリリースし、顧客からのフィードバックを迅速に反映。開発チーム自らが製品を日常的に利用するドッグフーディングや、PMM主催の勉強会を通じて、全部門一体で顧客理解を深める文化を醸成しています。
7. 『楽楽精算』15年の進化と未来への挑戦 〜経理の”楽”から、すべての働く人の”楽”へ〜
登壇者:楽楽精算開発部 開発2課 課長 高波 顕二郎
15年以上の歴史を持ち、導入社数1.9万社を超えるまでに成長した『楽楽精算』。その成長は、電子帳簿保存法やインボイス制度といった法制度ニーズへの迅速な対応によって加速してきました。しかし、その長い歴史は150万行を超えるコードベースや700以上の画面といった技術的負債も生み出し、開発スピードの低下という課題に繋がっていました。
本セッションでは、これまで注力してきた「経理担当者の楽」の実現に加え、今後は経費精算に不慣れな「申請者の楽」も実現すべくUI/UXの根本的な改善に着手していることが語られました。さらに、AIエージェントが自律的に経費精算を行う未来を見据え、レガシーな開発から脱却するための技術戦略として、モダンな新基盤の構築とAI駆動開発を両輪で進める挑戦が紹介されました。
クロージングトーク:AI開発の最前線と未来
登壇者:
大阪開発統括部 統括部長 矢成 行雄、東京開発統括部 プロダクト部 副部長 稲垣 剛之、AIエージェント開発課 課長 石田 浩章
イベントの最後には、AI開発を牽引する3名によるクロージングトークが行われました。 ここでは、各プロダクトへのAI機能の実装や、開発本部全体でのAIツール活用など、セッション本編では語りきれなかったテーマについて深掘りしました。
AI開発の組織体制について、ラクスでは単一の部門が集約的に開発するのではなく、各事業部の事情に合わせて多様なスタイルで取り組んでいることが語られました。 例えば、プロダクトマネージャーとデザイナーが所属するプロダクト部では、複数製品を横断する形でAIのロードマップ策定に関与しています。 一方で、新設されたAIエージェント開発課では、事業部直下に開発・営業・CSが一体となったコンパクトなチームを組成し、意思決定のスピードを重視した開発を進めています。
AIの進化に伴いエンジニアに求められるスキルについて、「審美眼」「適応力」「言語化能力」の3つが挙げられました。 AIが生成したアウトプットが本当に正しいかを見抜く力、変化の早い技術や常識を常にアップデートしていく力、そしてAIが理解できる形でコンテキストを的確に伝える力が、今後ますます重要になるとの展望が語られました。
おわりに
改めて、「RAKUS Tech Conference 2025」にご参加いただいた皆様、そしてご協力いただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました。
今回のカンファレンスを通じて、ラクスの各プロダクト開発チームが、それぞれの事業フェーズや市場環境の中で、いかに「顧客志向」を貫き、それを実現するために組織や開発プロセスを柔軟に変化させ、新しい技術に挑戦し続けているか、その一端を感じていただけたなら幸いです。
今後もラクスは、「顧客志向のSaaS開発組織」として、お客様の期待を超える価値を提供できるよう、真摯にプロダクト開発と向き合ってまいります。引き続き、ラクス開発本部の活動にご注目ください!


コメント