はじめに
どれだけ技術を学んでも、どれだけ正しいプロセスを知っていても、燃え尽きてしまったら意味がない。才能ある若者たちが最初は誰よりも速く理解して、誰よりも多くのコードを書いていたのに、数ヶ月後には姿を見せなくなる。「疲れた」と言って離れていく。
逆に、最初は遅くても数年経った今も黙々と学び続けている人たちがいる。彼らに共通しているのは、自分を大切に扱う習慣を持っていることだった。ちゃんと眠る。ちゃんと食べる。ちゃんと休む。そしてちゃんと掃除する。その中でも最も基本的な実践が、掃除だ。
在宅勤務を始めて六年目のある朝、ふと自分の部屋を見回した。
今、部屋は比較的綺麗だ。床に物は落ちていない。デスクの上も整理されている。技術書も本棚に並んでいる。窓を開けて空気を入れ替える習慣もついた。カーテンも開いていて、部屋の中は明るい。
30歳のエンジニア、独身。在宅勤務という働き方は自由をくれたはずなのに、気づけば自分は4畳半の部屋の中で完結した生活を送っている。仕事もする。プログラミングもする。読書もする。ブログも書く。趣味もある。
孤独は嫌いではない。むしろ好きだ。一人で考える時間、一人でコードを書く時間、一人で本を読む時間。誰にも邪魔されず、自分のペースで物事に向き合える時間。これは孤独であって、寂しさではない。寂しいと孤独は別物だ。孤独は選べるが、寂しさは選べない。
でも私生活がぐちゃぐちゃになってしまうと、自分のプライベートも引きずられて悪くなる。掃除をしなくなる。自炊をしなくなる。身だしなみが雑になる。運動をしなくなる。風呂に入らなくなる。これらが崩れ始めると、部屋は散らかり、仕事も集中できなくなり、趣味も楽しめなくなり、選んだはずの孤独が、望まない寂しさに変わっていく。
掃除は、精神の指標になる。部屋を見れば、今の自分の精神状態が分かる。乱れている時は心も乱れている。整っている時は心も整っている。
結局、最も重要なのは燃え尽きずに続けることで、そのために必要なのは自分を大切に扱うことで、その最も基本的な実践が掃除なのではないか。この記事は、そんな仮説を自分自身で検証するために書いている。
掃除とは何か。なぜ自分は掃除ができなくなるのか。そして掃除することで何が変わるのか。表面的な整理整頓の話ではなく、もっと根本的な、自分をどう扱うかという話だ。
このブログが良ければ読者になったり、nwiizoのXやGithubをフォローしてくれると嬉しいです。では、早速はじめていきます。
掃除できない理由は全て言い訳だ
「忙しいから掃除できない」。でも本当にそうか?毎日Twitterを見て、YouTubeのショート動画を延々と見ている。気づけば一時間、二時間が過ぎている。つまり、時間がないのではない。掃除を優先していないだけだ。
「疲れているから」という言い訳もある。でも実は、散らかった部屋で過ごしていることが疲れの原因かもしれない。視界の隅に常にゴミや散らかったものが入ってきて、それが無意識のストレスになっている。朝起きたときにすでに憂鬱で、仕事を始める前からエネルギーが削がれている。だから疲れる。そして疲れているから掃除しない。この悪循環。
「どうせすぐ散らかるから」という諦めもある。以前掃除したけど三日後には元通りだった。でもなぜか。綺麗にした後、何も仕組みを変えていなかったからだ。服を脱いだら床に置く習慣、ゴミが出たらデスクに置く習慣、本を読んだら床に積む習慣。掃除をしたというより、一時的に物を移動させただけだった。
これらの言い訳を並べてみて気づく。どれも本質的な理由ではない。本当の理由はもっと深いところにある。「どうせ自分なんか」という、言葉にならない諦めが。
部屋を整えることが心を整える
よく「部屋の乱れは心の乱れ」と言われる。でもこの言葉は因果関係が逆だ。
「部屋の乱れが心を乱す」のだ。そしてもっと正確に言えば「部屋を整えることが心を整える」。
心という曖昧なものを直接コントロールすることは難しい。でも部屋という物理的な空間は、手を動かせば変えられる。服をハンガーにかける。ゴミを捨てる。床を拭く。これらは全て、具体的で、実行可能で、結果が目に見える行動だ。
そしてこれらの行動が、不思議なことに心に作用する。綺麗な部屋で目覚めると、一日の始まりが違う。整理されたデスクで仕事をすると、思考がクリアになる。物が少ない空間にいると、頭の中も軽くなる。
部屋を整えることは、心を整えるための、最も具体的で確実な方法なのだ。
掃除は自分への態度を訓練する修行だ
掃除は単に「清潔にする」ための行動だと思われがちだ。でも実は、もっと深い意味を持っている。
自分をどう扱うかを、身体に教えている訓練なのだ。
掃除とは、「自分の空間を整える力が自分にある」と確認することだ。散らかった部屋を見て「どうせ自分には無理だ」と諦めるのではなく、一つずつ片付けていく。床に落ちている服を拾う。ゴミを捨てる。デスクを拭く。この行為を通じて「自分には変える力がある」と身体で理解する。
これは掃除だけではない。自炊なら「自分のために手を動かす価値がある」と身体が覚えること。身だしなみを整えるのは「私は丁寧に扱っていい存在だ」と身体に教えること。運動することは「自分の身体に投資する価値がある」と確認すること。風呂に入ることは「私は清潔でいていい存在だ」と身体に教えること。
しかし、その中でも掃除は最も基本的で、最も効果が目に見えやすい実践だ。
「どうせ自分なんか」と思って放っておく時間が続くと、それらの行為がどうしても億劫に感じて、身体は「私は放っておかれて当然なんだ」と学んでしまう。
逆に言えば、少しずつでも、適当でも、掃除をしていくことで、「自分は守られていい」「手をかけられていい」と身体が再び信じ始める。
これは精神論ではない。実際に起きることだ。部屋を掃除した日の夜、なぜか少しだけ自己肯定感が上がる。
掃除は、自分への態度を訓練する修行なのだ。
放置のサイクルと手入れのサイクル
放置のサイクル
朝起きる。部屋が汚い。気分が重い。でも掃除する気力がない。「今日は忙しいから」と自分に言い訳をする。朝食も作らない。シャワーも浴びない。適当な服を着る。仕事を始める。集中できない。視界の隅にゴミが見える。気が散る。効率が落ちる。疲れる。夜になる。もっと疲れている。掃除なんてできない。自炊もめんどくさい。風呂に入るのもめんどくさい。運動なんてもってのほか。「明日やろう」と思う。眠る。
次の日も同じ。部屋は昨日より汚い。服がもう一枚増えている。ゴミがもう一つ増えている。気分はもっと重い。でも何もする気力はもっとない。そしてまた「明日やろう」と思う。
一週間後、すべてが荒れ果てている。部屋は散らかり、床はほとんど見えない。デスクは物で埋まっている。空気は淀んでいる。そして自分の気持ちも荒れ果てている。「もうどこから手をつけていいか分からない」という諦めが支配している。
毎日、放置という行動を通じて、「お前は放っておかれて当然だ」というメッセージを自分自身に送り続けている。
手入れのサイクル
朝起きる。部屋が綺麗。気持ちがいい。窓を開ける。空気を入れ替える。ベッドを整える。たった一分の作業だが、これだけで一日の始まりが違う。シャワーを浴びる。髪を整える。清潔な服を着る。朝食を作る。簡単なものでいい。温かいご飯。身体が目覚める。
仕事を始める。デスクが綺麗だから集中できる。必要なものがすぐ見つかる。思考がクリア。コードがスムーズに書ける。効率が上がる。気持ちがいい。昼休み、食器をすぐ洗う。軽く散歩する。身体を動かす。
夜、仕事を終える。運動する日もある。しない日も軽くストレッチする。夕食を作る。自分のために作った温かいご飯。シャワーを浴びる。床に落ちているものを片付ける。ゴミを捨てる。読んだ本を本棚に戻す。合計十分。でもこの十分が、明日の自分を助ける。
身体は学習する。「私は手をかけられる存在だ」と。「私の空間は整っていていい」と。「私は価値がある」と。
行動が、その人の存在の意味を決める。言葉ではなく、行動が。毎日の小さな選択が、自分をどう扱うかを決めている。
規律という美学
部屋が散らかっている時の自分は、不思議なことに、あらゆる面が乱れている。時間管理も散らかる。締切ギリギリになって慌てる。生活のあらゆる面は繋がっていて、一つの領域での乱れは、他の領域にも波及する。
逆に、部屋を整えている時期の自分は、あらゆる面が整っている。朝、決まった時間に起きられる。約束を守れる。締切を守れる。自分との約束も守れる。そしてこの規律が、自分という存在に秩序をもたらす。
美しさとは、日々の規律ある行動から生まれる副産物なのではないか。
一つ一つの動作に美を宿すこと。服を畳むときに丁寧に畳む。食器を洗うときに丁寧に洗う。掃除をするときに隅々まで拭く。これらの「めんどくさい」行為が、実は自分を美しくしている。
誰も見ていない。在宅勤務だから誰にも会わない。だから適当でいい。そう思って過ごしていると、その「適当さ」が身体に染み込んでいく。
でも逆に、誰も見ていなくても、自分のために丁寧に生きる。その選択が、自分を美しくする。
掃除は「修行」として捉えるべき実践なのだ。
小さく始めるという勇気
ある日、決意した。「今日から毎日掃除をする」と。でも夜には忘れていた。三日目には諦めていた。「やっぱり自分には無理だ」と。
問題は、始め方が大きすぎたことだ。「毎日掃除をする」というのは、実は途方もなく大きな変化だ。
でもある時、試しに小さく始めてみた。「朝起きたら、ベッドを整える。それだけ」。
これなら一分もかからない。簡単すぎる。でもこれを続けた。一週間、二週間、一ヶ月。気づけば習慣になっていた。
そして不思議なことに、ベッドを整える習慣ができると、他のことも少しずつやりたくなってきた。「どうせベッドを整えるなら、カーテンも開けよう」「どうせカーテンを開けるなら、窓も開けよう」「どうせ窓を開けるなら、ゴミも捨てよう」。
小さな一歩が、次の一歩を呼ぶ。
完璧を求めて何もしないより、不完全でも小さく始める方が、ずっと前に進める。
一日五分の掃除と、週に一回の大掃除、どちらが効果的か。前者だ。なぜなら習慣になるから。
小さく始めることは、実は最も大きな勇気を必要とする。なぜなら、小さすぎて効果がないように感じるから。「たったこれだけで意味があるのか」という疑念と戦わなければならない。
でも意味はある。確実にある。身体は小さな変化を記憶する。そして小さな変化の積み重ねが、大きな変化になる。
おわりに
この記事を書きながら、自分の部屋を見回している。
今、部屋は比較的綺麗だ。床に物はほとんど落ちていない。デスクの上も整理されている。窓を開けて空気を入れ替える習慣もついた。これらの小さな習慣が、気持ちを支えている。仕事にも集中できる。コードを書くのも、ブログを書くのも、本を読むのも楽しい。
掃除は、精神の指標になる。今、部屋が比較的綺麗なのは、今の精神状態が比較的安定しているということだ。でも油断すると、すぐに乱れる。だから毎日少しずつ手をかけ続ける。
才能があっても燃え尽きたら意味がない。理解が速くても続かなければ意味がない。結局、長く続けた人が、最も遠くまで行く。そして長く続けるために必要なのは、派手なスキルでも高度な知識でもなく、自分を丁寧に扱う日々の習慣だ。
掃除は単なる家事ではない。自分への態度を訓練する修行であり、自分という存在をどう扱うかを身体に教える実践だ。そして何より、燃え尽きないための、最も基本的な自己防衛の手段なのだ。
在宅勤務で過ごす30歳の自分にとって、掃除は生き延びるための技術になった。孤独は好きだ。一人で考える時間、一人でコードを書く時間、一人で本を読む時間。誰にも邪魔されない自由。でもその孤独を愛するためには、まず自分の空間を整える必要があった。部屋を整えることで、心を整える。空間に秩序をもたらすことで、人生に秩序をもたらす。そして集中して仕事ができる。コードが書ける。ブログが書ける。本が読める。選んだ孤独を、寂しさに侵食されずに生きられる。
自分を大切にするということ。それは掃除をすること、自炊をすること、身だしなみを整えること、運動をすること、風呂に入ること。これらすべてが大切だ。でもその第一歩が、掃除なのだ。
「どうせ自分なんか」という声が聞こえたら、まず床に落ちている服を一枚拾う。ゴミを一つ捨てる。デスクを一度拭く。たったそれだけでいい。
その小さな行動が、「自分は手をかけられていい」というメッセージを、自分自身に送る。そして身体がそれを覚える。少しずつ、少しずつ、「自分は大切にされていい存在だ」と信じ始める。
完璧を目指す必要はない。毎日完璧に掃除する必要もない。ただ、少しずつでも、適当でも、自分に手をかけ続けること。それが掃除の本質であり、同時に自分を整えることの本質であり、そして燃え尽きずに続けるための、最も確実な方法なのだ。
技術は大切だ。知識も大切だ。仕事も大切だ。プログラミングも大切だ。読書も大切だ。ブログも大切だ。趣味も大切だ。孤独を愛することも大切だ。でも最も大切なのは、自分を大切にすることだ。そしてその第一歩が、自分の部屋を掃除することなのかもしれない。
おい、部屋を掃除しろ。
それは命令ではなく、自分自身への、静かな呼びかけだ。長く続けるために。燃え尽きないために。そして、自分を大切にするために。

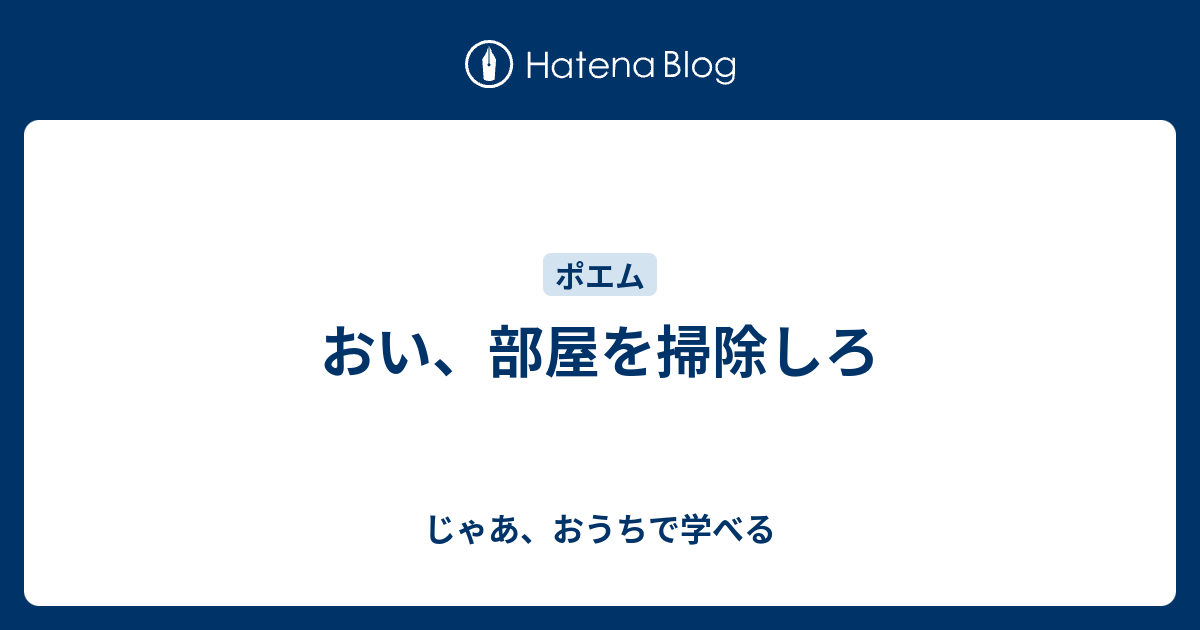
コメント