はじめに
こんにちは。 マネーフォワード 福岡開発拠点でSREとして働いているM-Yamashita です。
2025年10月27日(月)に東京で開催された、Observability Conference Tokyo 2025に参加しました!
この記事ではイベントレポートとして、カンファレンスの雰囲気や特に印象に残ったセッションについてお伝えします。

特に印象に残ったセッション
キーノートセッション Building Affordable Observability: Strategy to Implementation
このセッションでは、コストを抑えつつオブザーバビリティを効率的に実現するための戦略と、その実践方法について解説がありました。
特に印象に残ったのは、ユーザー体験の重視と、データにReduce・Reuse・Recycleを適用するという2点です。
セッションでは “User experiences ≈ marbles” と表現されていました。これは、ユーザー体験がビー玉のように多種多様で、それぞれが異なる特性を持っていることを示唆しています。個々の特性を測定し可視化することが、ユーザー体験の向上につながるのだと感じました。
また、測定におけるデータの取り扱いについてReduce・Reuse・Recycleに触れ、「Stop writing read-never data」というメッセージが伝えられました。
これは非常に重要な指摘ですが、実践するのは難しい点でもあります。例えば、トラブル調査のために良かれと思って集めた大量のデータが、かえってノイズになることもあります。どのデータを残し、どのデータを捨てるべきか。そのためには、そもそも「何のためにそのデータを集めるのか」という目的を常に問い直し、見極めていく必要があると感じました。
プロファイルとAIエージェントによる効率的なデバッグ
このセッションでは、プロファイルの重要性と、プロファイルの情報をAIエージェントに読み解かせることでデバッグを効率化する方法が紹介されました。
プロファイルを有効にしても、それを人間が読み解くのは難しいという課題があります。特に、問題のあるコードが不慣れな言語で書かれていたり、仕様が複雑だったりする場合にはなおさらです。そうした場面でAIエージェントのサポートを得ることで、問題箇所を迅速に特定できるというのは、非常に魅力的なアプローチだと感じました。
さらに、このアプローチは副次的な効果も期待できるとのことでした。AIエージェントが問題解決の過程でどのようなコマンドを使用しているかを確認することで、開発者自身のスキルアップにもつながるとのことでした。このように効率的に学びを深めていくという面でも、優れた手法だと感じます。
現場の壁を乗り越えて、「計装注入」が拓くオブザーバビリティ
このセッションでは、自動計装の仕組みをコンテナやプロセス単位でシステムに自動的に組み込む手法を「計装注入」と定義し、その有用性が解説されました。
計装とは、トレースやメトリクスなどを収集するためのコードをアプリケーションに組み込むことを意味します。この計装には手動軽装と自動計装の2種類があり、スライドではそれらの違いを以下のように説明されていました。
- 手動計装: テレメトリーシグナルを取得するために、アプリケーションコードに直接API/SDKの実装を施す軽装方式
- 自動計装: テレメトリーシグナルを取得するために、アプリケーションコードに変更を加えず、言語特有の機能で関数をラップして、SDKの実装を施す軽装方式
自動計装を導入する際の課題として、多言語・分散システムやレガシーシステムにおいて、それぞれ次のような点が挙げられていました。
- 多言語・分散システム: 言語ごとに計装手法が異なってしまうためオーバーヘッドが高いこと
- レガシーシステム: コードの変更承認プロセスが重いこと
私自身も同様のシステムに携わった経験があるため、これらの課題には非常に共感できました。
この課題に対し計装注入のアプローチとして、OpenTelemetry OperatorとOpenTelemetry Injectorの2つを紹介されていました。
OpenTelemetry Operatorでは、Operatorが自動計装ツールをpodに組み込む設定を入れること各言語の自動計装ができると説明されていました。マニフェストにannotationを追加し自動計装ツールを適用することで、podのInit Containersとして自動的に作られるようです。
OpenTelemetry Injectorは、Linux上で共有ライブラリをプリロードして自動計装を実現するようでした。
どちらの手法も先述の課題を解決する強力な選択肢だと感じました。その一方で、これらの注入の仕組みは攻撃にも利用されうるためその動作を深く理解し、検知できる仕組みを併せて用意しておくことが重要だという点も心に留めておきたいです。
廊下や懇親会での交流
カンファレンスでは、セッションだけでなく、廊下や懇親会での交流も大きな楽しみの一つです。
スポンサーブースを回った際には、各社のエキスパートの方々に、現在抱えている課題について技術的な相談をさせていただき、今後のアプローチについて有益なアドバイスをいただきました。また、別のブースでは脆弱性検知について気になる点があり、そちらについても詳しくお話を伺うことができました。
またこのカンファレンスで、オブザーバビリティ・エンジニアリングの本の著者であるキーノートセッションのLizさんや訳者の山口さん、大谷さんによるサイン会もありました。自分が追いかける人が目の前にいるというのはとても素晴らしい体験でした。

交流会では、初めてお会いする方々と情報交換をしたり、以前別のカンファレンス運営でご一緒した方と久しぶりに再会したりと、多くの出会いがありました。そうした会話の中で、互いの組織が抱える課題を共有したり、過去の経験について語り合ったりできたことも大きな収穫です。こうしたリアルな場での交流もカンファレンスの魅力だと改めて感じました。
おわりに
Observability Conference Tokyo 2025を開催してくださった運営の皆さま、素晴らしいセッションを提供してくださった登壇者の皆さま、そしてスポンサー企業の皆さま、本当にありがとうございました!
次回の開催は未定とのことですが、もし開催される際には、ぜひまた参加したいと思います。
最後に、マネーフォワード福岡開発拠点ではエンジニアを募集しています!
ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください。

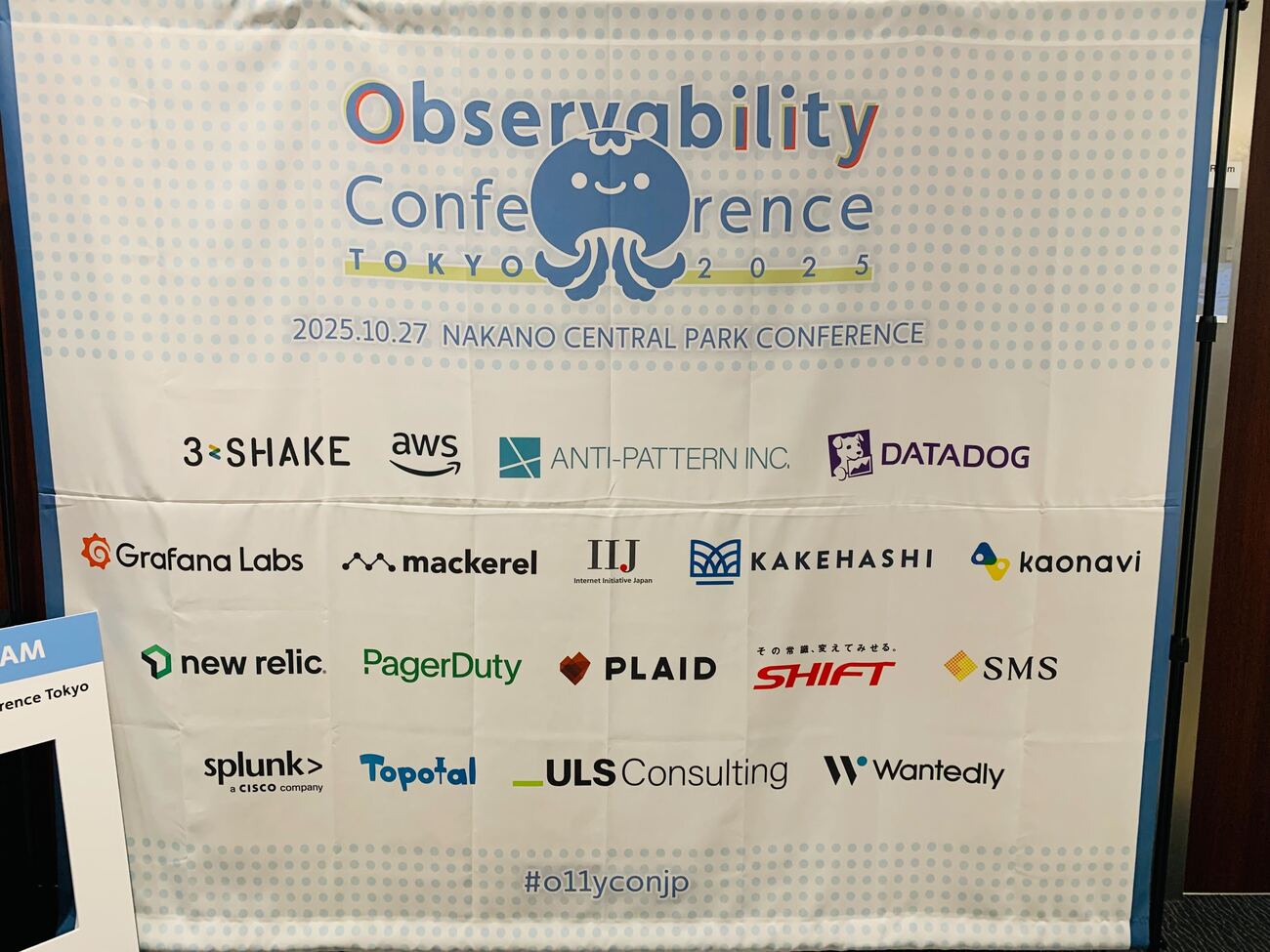
コメント